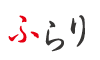学校で上履きを履くのはなぜ?
しかし、チコちゃんは知っています。
出入口を一つにするため~。
教えてくれるのは、元京都精華大学 人文学部特任教授 中西宏次さん。
上履きを履くのは校内を汚してしまうからだというふうに考えている人が多いですが、実は「出入口を一つにするため」だと言えるんです。
日本→玄関先で靴を脱ぐ
江戸時代に庶民が通った寺子屋でも生徒たちは履き物を脱いで学んでいた。
寺子屋→学校の前身といわれる教育施設
寺子屋はお寺や先生の自宅を使用。
履き物を脱いで学んでいた。
この時はまだ上履きはありませんでした。
上履きをはくようになったきっかけは、明治時代の初めに政府が作った「近代化政策」にあると言われています。
明治5年、政府は欧米諸国のような近代的な国家を目指す一環として、子どもの教育を義務付けた。
寺子屋→学びたい人だけ通う。
明治5年以降は多くの子どもが義務教育の対象になった。
寺子屋の建物だけでは足りなくなり、初めて学校が建てられた。
その時に建てられたのが洋風建築。
洋風建築は履き物を脱いで上がる場所として、玄関が基本的になかった。
しかし、明治8年に建てられた山梨県甲斐市の睦沢学校の平面図を見てみると、洋風建築なのに「土足室」が設けられたいた。
明治9年に建てられた長野県松本市の旧開智学校の平面図にも「傘履物置場」という文字があった。
生徒は履き物を脱いでいた。
日本古来の履き物を脱いで上がるという習慣を簡単に変えることはできなかった。
洋風建築の校舎+履き物を脱ぐ場所(昇降口)
日本独特の建物に。
スポンサーリンク
しかし洋風建築の校舎は床が板敷になっていて、冬場はかなり冷たくなってしまうことなどから、履き物なしでは過ごすには適していなかった。
そこで履き物を脱いでから上履きには履きかえることに。
学校で上履きを履くのは…日本と欧米の履物文化ミックス
外履き→上履きに履きかえる
げた箱がある昇降口を必ず通る
これによって校舎への出入り口を一つにすることができるのです。
出入り口が一つになると、児童をしっかり見守ることができる。
安全が確保できる。登下校に児童の様子を把握しやすいので、今でも学校は上履きに履きかえる。

学校で上履きを履くのはなぜ?
出入口を一つにするため~。
番組公式ページへ